- メディア
- 2025.10.15
誹謗中傷の対策|企業がSNSで取るべき法的措置と対処法を解説

SNSの普及に伴い、企業に対する誹謗中傷は深刻な経営リスクとなっています。
一度ネガティブな情報が拡散されると、企業ブランドや信頼性の回復は容易ではありません。
この記事では、企業がSNSで誹謗中傷を受けた際の具体的な対処方法や、法律に基づいた法的措置の流れを解説します。
事前の予防から事後の対応まで、誹謗中傷の対策として知っておくべき知識を網羅的に説明します。
企業が知っておくべき誹謗中傷の定義と判断基準
誹謗中傷とは、根拠のない悪口や嘘を広め、他人の名誉や社会的評価を低下させる行為を指します。
企業活動においては、正当な批判やサービスに対する意見、口コミと、誹謗中傷との線引きが重要です。
すべてのネガティブな投稿が違法となるわけではなく、その内容が事実に基づいているか、公共の利害に関するものかといった点が判断基準となります。
どの投稿が法的措置の対象となるかを見極めることが、適切な対応の第一歩です。

どこからが違法?正当な批判や口コミとの明確な違い
誹謗中傷と正当な批判を分ける基準は、内容の「公共性」「公益性」「真実性・真実相当性」にあります。
例えば、製品の欠陥を指摘する口コミでも、それが消費者の利益を図る目的(公益性)であり、公共の関心事(公共性)で、内容が事実(真実性)であれば、正当な批判と見なされ違法性は問われません。
一方で、具体的な根拠を示さず「あの会社は反社会的勢力とつながっている」といった事実に反する内容を投稿する行為は、企業の社会的評価を不当に貶めるため、名誉毀損にあたる可能性が高くなります。
表現が個人の感想や意見の範囲を超え、人格攻撃や事実に基づかない断定的な表現になっている場合は、誹謗中傷と判断されやすくなります。
誹謗中傷で成立する可能性のある3つの罪
企業への誹謗中傷では、主に「名誉毀損罪」「侮辱罪」「信用毀損罪・業務妨害罪」の3つの犯罪が成立する可能性があります。
名誉毀損罪は、公の場で具体的な事実を挙げて社会的評価を下げる場合に成立します。
内容が真実でも罪に問われることがあります。
侮辱罪は、事実を挙げずに「バカ」「無能」といった抽象的な表現で相手を侮辱した場合に適用されます。
信用毀損罪・業務妨害罪は、虚偽の情報を流して企業の経済的な信用を傷つけたり、正常な業務運営を妨害したりする行為です。
例えば「あの飲食店の食材は使いまわしだ」といった嘘の情報を流す行為がこれに該当します。
なぜ企業はSNSで誹謗中傷の標的になるのか?その主な原因
企業がSNSで誹謗中傷の標的になりやすい背景には、SNSが持つ特有の性質が関係しています。
誰もが気軽に情報を発信できる手軽さの一方で、その匿名性から攻撃的な投稿が生まれやすい環境があります。
また、情報の拡散力が非常に高いため、一つの投稿が瞬く間に広がり、大きな騒動へと発展しやすいリスクを常に抱えています。
これらの特性が、企業への不満や誤解を増幅させ、誹謗中傷という形で表面化させる主な原因となっています。
匿名で投稿できることによる攻撃性の高まり
SNSの多くは、実名を出さずに利用できる匿名性の高いプラットフォームです。
この匿名性は、発信者が特定されにくいという安心感を生み、普段は抑制されている攻撃的な感情を表に出しやすくさせます。
対面では決して口にしないような過激な言葉や、根拠のない悪意に満ちた嘘でも、匿名の陰に隠れることで気軽に投稿できてしまいます。
自分の発言に対する責任感が薄れるため、倫理的なハードルが下がり、企業に対する一方的で攻撃的な誹謗中傷が増加する一因となっています。
結果として、事実確認が不十分なまま、感情的な投稿が繰り返される事態を招きます。
瞬時に情報が広まるSNS特有の拡散力
SNSは情報の拡散スピードが非常に速いという特徴を持っています。
特にTwitter(現X)のリツイート機能やFacebookのシェア機能は、ボタン一つで情報を瞬時に多くの人へ共有できます。
企業に対する誹謗中傷の投稿が一つでも行われると、それが多くのユーザーの共感を呼んだり、興味を引いたりした場合、あっという間に拡散されてしまいます。
一度拡散された情報は、元の投稿が削除されたとしても、コピーやスクリーンショットが残り続け、完全に消去することは極めて困難です。
この強力な拡散力により、局所的な不満が全社的な危機へと発展するリスクが常に存在します。
SNSで誹謗中傷を発見した際に企業が取るべき4つのステップ

インターネット上で企業への誹謗中傷を発見した場合、冷静かつ迅速な対応が求められます。
感情的な反論は事態を悪化させるだけであり、正しい手順を踏むことが重要です。
ここからは、企業が取るべき具体的な対策方法を4つのステップに分けて解説します。
証拠を確保し、投稿の削除を求め、必要であれば投稿者を特定して法的措置を取るという一連の流れを理解することが、被害を最小限に抑える鍵となります。
ステップ1:投稿のURLやスクリーンショットで証拠を保全する
誹謗中傷の投稿を発見したら、まず最初に行うべきは証拠の保全です。
投稿者が後から投稿を削除したり、アカウントを消したりする可能性があるため、法的手続きを進める上で不可欠な証拠を確保します。
具体的には、投稿内容、投稿日時、アカウント名、そして投稿ページのURLがすべて含まれるように、PCのブラウザやスマートフォンのアプリ画面のスクリーンショットを撮影します。
画像だけでなく、可能であればPDF形式でページ全体を保存したり、動画で撮影したりすることも有効です。
この証拠が、後の削除要請や発信者情報開示請求において、権利侵害を証明するための重要な資料となります。
ステップ2:サイト管理者やSNS運営会社に削除を要請する
証拠を確保した次に、投稿がなされたSNSの運営会社やサイトの管理者に対して、投稿の削除を要請します。
多くのプラットフォームでは、利用規約で名誉毀損やプライバシー侵害にあたる投稿を禁止しており、違反が認められれば投稿は削除されます。
各SNSに設置されている問い合わせフォームや「報告」機能を通じて、どの投稿が利用規約のどの部分に違反し、どのような権利侵害を受けているのかを具体的に説明して申請します。
ただし、プラットフォーム側の判断によっては削除されないケースもあるため、必ずしも要請が通るとは限りません。
この方法は、投稿者を特定せずに迅速な解決を図りたい場合に有効です。
ステップ3:発信者情報開示請求で投稿者を特定する
投稿の削除だけでは不十分で、投稿者への損害賠償請求などを検討する場合には、発信者を特定する手続きが必要です。
匿名で投稿された場合でも、「発信者情報開示請求」という法的な手続きを踏むことで、投稿者の氏名や住所といった個人情報を特定できる可能性があります。
この手続きは、まずSNS運営会社に対してIPアドレスなどの開示を求め、次にそのIPアドレスから判明した経由プロバイダに対して契約者情報の開示を求める、という2段階の裁判手続きを経るのが一般的です。
手続きは複雑で時間を要しますが、法的責任を追及するためには不可欠なステップです。
ステップ4:投稿者に対して損害賠償請求などの法的措置を取る
発信者情報開示請求によって投稿者が特定できた後は、その個人に対して損害賠償請求や謝罪広告の掲載といった民事上の法的措置を取ることが可能になります。
損害賠償請求では、売上減少や対応にかかった費用、企業イメージの低下による無形の損害(慰謝料)などを請求します。
また、悪質なケースでは名誉毀損罪などで刑事告訴することも選択肢の一つです。
なお、損害賠償請求権は損害および加害者を知った時から3年で時効となるほか、プロバイダが保有する通信ログの保存期間も限られているため、迅速な対応が求められます。
誹謗中傷への対応で企業がやってはいけないNG行動
SNSでの誹謗中傷に対しては、迅速かつ慎重な対応が求められますが、その過程で誤った行動を取ると、かえって事態を悪化させ、企業の信頼をさらに損なう危険性があります。
感情的な対応や準備不足の行動は、炎上を拡大させたり、その後の法的手続きを不利にしたりする原因となりかねません。
ここでは、企業担当者が誹謗中傷に対応する際に、絶対に避けるべきNG行動について具体的に解説します。
感情的に反論してさらなる炎上を招くこと
企業や自社製品を中傷する投稿に対し、公式アカウントが感情的に反論することは避けるべきです。
担当者の個人的な感情で反論してしまうと、相手を刺激し、口論のような不毛なやり取りに発展しかねません。
このような態度は、他のユーザーから見ても企業の未熟さや品位の欠如と受け取られ、新たな批判の火種となり、さらなる炎上を招きます。
対応する際は、あくまで企業の公式な立場として、冷静かつ客観的な事実に基づいた毅然とした態度を貫くことが重要です。
個人的な意見や感情を交えず、組織として統一された見解を発信するように徹底します。
証拠を確保せずに投稿の削除を依頼すること
誹謗中傷の投稿を発見し、一刻も早く削除したいという気持ちは当然ですが、証拠を確保する前に削除依頼を出すのは非常に危険です。
もし投稿が削除されてしまうと、その投稿が実際に存在したことを証明する客観的な証拠が失われてしまいます。
その結果、後から投稿者を特定して損害賠償請求を行おうとしても、権利侵害の事実を立証できず、法的手続きを進めることが極めて困難になります。
どのような対応を取るにせよ、まずはURLや投稿日時、内容がわかるスクリーンショットなどを確実に保存し、証拠を保全するという手順を必ず踏むようにしてください。
被害を放置して企業イメージの低下を招くこと
「そのうち忘れられるだろう」と誹謗中傷を安易に考え、放置することも重大なNG行動です。インターネット上に一度書き込まれた情報は、時間の経過によって消失するケースがある一方で、半永久的に残り続けるものも存在し、検索エンジンなどを通じて閲覧可能な状態になることがあります。放置された悪評は、顧客や取引先、金融機関、さらには就職活動中の学生など、多くのステークホルダーの目に触れる機会があります。これにより、企業イメージやブランド価値が徐々に低下し、売上減少や採用活動の不振、取引の停止といった具体的な経営ダメージにつながる可能性があります。被害の拡大を防ぐためにも、早期の段階で適切な対応を取ることが不可欠です。
誹謗中傷の被害を未然に防ぐための企業の予防策

誹謗中傷は、問題が発生してから対処する「事後対応」だけでなく、被害を発生させないための「事前予防」が重要です。
日頃から社内体制を整備し、リスクの芽を摘んでおくことで、万が一の事態が発生した際にも被害を最小限に食い止めることができます。
ここでは、企業が取り組むべき具体的な予防策として、社内ガイドラインの策定と、定期的な監視体制の構築について解説します。
SNSの利用ガイドラインを社内で策定・共有する
従業員個人のSNS利用が、意図せず企業の誹謗中傷や炎上の引き金になるケースは少なくありません。
これを防ぐためには、従業員が遵守すべきSNS利用に関する明確なルールを定めたガイドラインを策定し、社内で共有することが不可欠です。
ガイドラインには、会社の機密情報や顧客の個人情報を投稿しない、他者を誹謗中傷する内容や差別的な発言をしない、といった基本的な禁止事項を盛り込みます。
また、会社の公式見解と誤解されるような発信を避けるための注意点なども記載します。
定期的な研修を通じて全従業員に周知徹底し、SNSリテラシーを向上させることが、内部からのリスクを低減させます。
定期的な監視で誹謗中傷を早期に発見できる体制を構築する
外部からの誹謗中傷を完全に未然に防ぐことは困難ですが、早期に発見し対応することで被害の拡大を防ぐことは可能です。
そのためには、自社名や商品・サービス名、役員名などのキーワードで、SNSや検索エンジンを定期的に監視する体制を構築することが重要です。
専門の監視ツールを導入したり、広報や法務部門に担当者を置いたりして、ネガティブな投稿をいち早く察知できるようにします。
問題のある投稿を発見した際に、誰が、どのように対応するかのフローをあらかじめ決めておくことも、迅速な初動対応につながります。
誹謗中傷の火種を小さいうちに消し止めるには、こうした地道な監視活動が効果的です。
誹謗中傷対策を弁護士に相談する3つのメリット
企業への誹謗中傷は、法的な判断が求められる複雑な問題です。
自社だけで対応しようとすると、誤った判断で事態を悪化させたり、手続きに手間取って時間を浪費したりする可能性があります。
そこで有効なのが、インターネット問題に詳しい弁護士への相談です。
専門家である弁護士に依頼することで、迅速かつ的確な対応が可能となり、企業が受けるダメージを最小限に抑えることができます。
ここでは、弁護士に相談する具体的なメリットを3つ紹介します。
法的な見通しを立てて最適な対応を判断してもらえる
ある投稿が法的に権利侵害にあたるか、名誉毀損や侮辱といったどの罪に該当しうるかの判断は、専門知識がないと難しいものです。
弁護士に相談すれば、過去の裁判例や法律に基づき、その投稿の違法性を客観的に評価してもらえます。
その上で、削除要請で済ませるべきか、発信者情報開示請求を経て損害賠償請求まで行うべきかなど、状況に応じた最適な対応方針について具体的な助言を得られます。
総務省など国や政府の機関が提供する情報も参考になりますが、個別の事案に即した法的な見通しを得られることが、弁護士に相談する大きな利点です。
複雑な法的手続きを迅速に進めることができる
発信者情報開示請求や損害賠償請求といった裁判手続きは、申立書の作成や証拠の提出など、非常に専門的で複雑です。
企業の担当者が本業の傍らでこれらの手続きを進めるのは、多大な時間と労力がかかり、現実的ではありません。
手続きに不備があれば、請求が認められないリスクもあります。
これらの煩雑な法的手続きをすべて弁護士に一任することで、企業は本来の業務に集中できます。
特に、証拠となる通信ログの保存期間は限られているため、迅速に手続きを進められる専門家のサポートは不可欠です。
今後の再発防止に向けた具体的なアドバイスを受けられる
弁護士の役割は、発生した問題への対処だけではありません。
今回の誹謗中傷がなぜ起きたのか、企業の広報体制や顧客対応に問題はなかったかなどを分析し、専門家の視点から再発防止策を提案してもらえます。
例えば、より実効性のある社内SNS利用ガイドラインの改訂や、従業員向けの情報リテラシー研修の実施、炎上リスクを低減するための広報戦略など、今後の企業活動に活かせる具体的で効果の高いアドバイスが期待できます。
長期的な視点で企業のレピュテーションリスクを管理していく上で、信頼できるパートナーとなります。
まとめ
SNSやネット掲示板における企業への誹謗中傷は、放置すればブランドイメージの低下や売上減少に直結する深刻な問題です。
被害を発見した際は、まず投稿のURLやスクリーンショットで証拠を保全し、感情的な反論は避けて冷静に対応することが求められます。
その上で、サイト管理者への削除要請や、弁護士を通じた発信者情報開示請求、損害賠償請求といった法的措置を検討します。
また、事後対応だけでなく、平時から社内ガイドラインの整備や監視体制の構築といった予防策を講じることも重要です。
自社での対応が困難な場合は、速やかに専門家である弁護士に相談し、法的観点から最適な解決策を見出すことが、企業を守る上で不可欠です。
UCWORLDが選ばれる理由

誹謗中傷関連の検索量が一定水準を超えると、サジェストや関連検索に定着しやすくなり、解除難度が一気に上がります。
拡散直後の初動(発見→記録→削除申請→公式説明の公開)が、のちの対処コストと期間を大きく左右します。
弁護士に相談して対策が完了するまでにどのくらいの時間がかかるでしょうか?
もしも、すぐに削除を開始したい場合に、同時並行したほうがよいのは、誹謗中傷ワードの削除です。
私たちの提供価値
- 即応:対象キーワードの出現を確認し、最短手順でサジェスト非表示の申請実務を進めます。
- 効果最大化:関連語の出現状況を踏まえ、優先度の高い語から順に処理して工数と期間を圧縮します。
すぐにご相談ください
検索候補に「(会社名) ブラック」「やばい」「違法」「詐欺」などが出たら、初動が肝心です。
スクリーンショット(会社名・候補語・日時が分かる画面)と、対象キーワードをお送りください。
進め方(標準フロー)
- 対象共有(キーワード/スクショ受領)
- 証拠形式の確認・整備
- サジェスト非表示の申請実行
- 結果報告と必要に応じた追随対応
料金
- 1ワード非表示:3万円〜
→詳しい料金や内容はこちらから
(対象語数と状況によりお見積りします。まずは簡易診断をお返しします。)
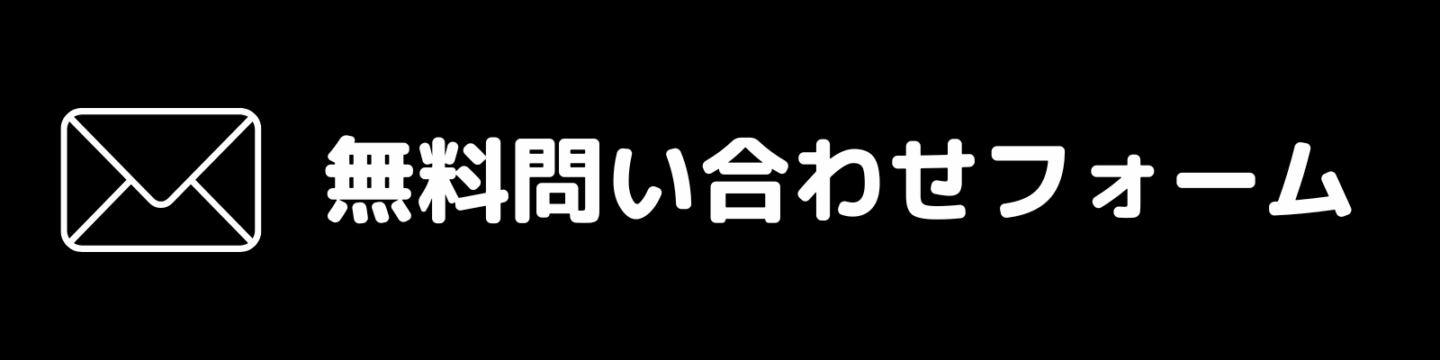

 お問い合わせ
お問い合わせ 資料請求
資料請求