- メディア
- 2025.11.14
SNS炎上【2025年最新】企業の事例と原因・リスク対策を解説

SNSの炎上とは、企業や個人の投稿に対して批判が殺到し、収拾がつかなくなる状態を意味します。
企業にとってSNS炎上はブランドイメージの失墜や売上減少に直結する深刻な経営リスクです。
この記事では、炎上の意味や具体的な事例について触れながら、その原因を分析し、企業が取るべき具体的な対策を解説します。
【2025年最新】SNSで実際に起きた企業の炎上事例

企業のSNS炎上は、最近のニュースでも頻繁に報じられており、その歴史の中で多くの有名企業が不祥事として扱われる事態に陥っています。
2025年に至るまで、大小さまざまな会社が炎上を経験しており、その事例は後進の教訓となっています。
ここでは、実際に起きた企業の炎上事例を原因別に一覧で紹介し、どのような投稿や対応が問題視されたのか、具体的な例を挙げて解説します。
不適切な表現・差別的な投稿による炎上事例
企業の公式アカウントや広告における不適切な表現は炎上の典型的な原因です。
特に、ジェンダー、人種、容姿などに関する配慮を欠いたワードを使用した内容は、差別的であるとして厳しい批判の対象となります。
過去には、有名タレントを起用したキャンペーンや、人気漫画とコラボレーションした企画の内容が、特定の属性を嘲笑していると受け取られ、大規模な不買運動に発展したケースがありました。
作り手側に差別の意図がなくとも、受け手がどう感じるかが重要であり、多様な価値観への深い理解がなければ、不用意な発言一つで企業の信頼を損なう事態を招きます。
従業員の不適切な言動が発覚した炎上事例
アルバイトや社員といった従業員個人の不適切な言動が、SNSを通じて拡散され、企業全体の責任問題へと発展する事例も後を絶ちません。
特に飲食店や医療現場など、高い倫理観が求められる職場で、従業員が店の商品で遊ぶ様子や、患者の個人情報を示唆する内容を投稿した騒動は社会に大きな衝撃を与えました。
これらの行為は「バイトテロ」とも呼ばれ、発覚後には当該従業員が解雇されるだけでなく、企業が謝罪に追い込まれ、甚大なブランドイメージの低下と経済的損失を被ります。
個人のアカウントからの投稿であっても、企業の看板を背負っているという自覚を促す教育が不可欠です。
顧客による迷惑行為から発展した炎上事例
近年、飲食店などを中心に顧客である一般人による迷惑行為の動画がSNSで拡散し、炎上するケースが頻発しています。
回転寿司チェーン「スシロー」でしょうゆ差しを舐める動画が拡散された事件は象徴的であり、多くの模倣犯も現れ社会問題化しました。
この種の炎上では、企業側も被害者である一方、店舗の衛生管理体制や迷惑行為への抑止力が問われることになります。
企業は警察へ被害届を提出するなど毅然とした対応を取る姿勢を示すことが求められます。
顧客の迷惑行為がYouTubeなどで拡散されることで、直接的な加害者でなくともブランドイメージが傷つくという新たなリスクが浮き彫りになりました。
企業の公式発表や対応が火種となった炎上事例
炎上が発生した後の企業の公式な対応が不適切であったために、さらに批判が拡大し、大炎上へと発展するケースは少なくありません。
問題となった投稿を説明なく削除したり、批判的なコメントを無視・放置したりする行為は、ユーザーの不信感を煽ります。
また、形式的な謝罪コメントや、社長自らが火に油を注ぐような発言をしたことで、事態がさらに悪化した事例も存在します。
炎上発生後の対応、いわゆる「火消し」は極めて重要であり、その後の企業の運命を左右します。
誠実さを欠いた対応は、最初の炎上よりも深刻なダメージをもたらす可能性があります。
情報漏洩や内部告発が原因の炎上事例
企業のずさんな管理体制が原因で顧客情報が漏洩したり、元従業員などから内部告発がなされたりすることで炎上するケースもあります。
情報漏洩が発生した場合、企業は個人情報保護法などの法律に基づく対応を求められるだけでなく、被害を受けた顧客からの信頼を完全に失います。
漏洩した情報が不正利用されるサイトで売買されるといった二次被害に発展することも考えられます。
また、内部告発によって企業の不正行為がSNSで暴露された場合、その内容が事実であれば、社会から厳しい批判を受け、事業の存続が危ぶまれる事態にまで発展する可能性があります。
キャンペーンや広告内容が批判を浴びた炎上事例
良かれと思って企画した広告やマーケティングキャンペーンが、意図せず批判を浴びて炎上する事例も数多く見られます。
特に、性的な表現やジェンダーに関する固定観念を助長するような内容は批判の的になりやすい傾向があります。
過去には、大手コンビニエンスストアのローソンが実施したキャンペーンや、ラーメン店、ホテルの広告案件が、女性蔑視や過度な表現であるとして炎上しました。
海外の価値観と日本のそれとのギャップが原因で、国外から批判が殺到するケースもあります。
注目を集めようとするあまり、社会の倫理観や多様性への配慮を欠いた広告は、逆効果になるリスクを常に抱えています。
企業SNSが炎上してしまう主な原因
SNSが炎上する背景には、いくつかの共通した原因が存在します。
炎上しやすい投稿や企業体質には特定のメカニズムがあり、その理由を理解することが予防の第一歩となります。
個人の認識不足といったミクロな問題から、企業全体のガバナンスの欠如というマクロな問題まで、炎上を引き起こす要因は多岐にわたります。
ここでは、過去の事例を基に、企業SNSが炎上してしまう主な原因とは何かを具体的に解説します。
担当者の認識不足や配慮に欠ける投稿
SNS運用担当者の知識や倫理観の欠如は、炎上の直接的な引き金となります。
特に、ジェンダー、人種、宗教、政治、容姿といったデリケートな話題に対して、無配慮な投稿をしてしまうことがトラブルの原因になりがちです。
担当者自身に悪意がなくとも、特定の集団を傷つけたり、差別を助長したりすると受け取られる表現を用いてしまうケースは後を絶ちません。
軽い気持ちで発信した一言が、企業の公式見解と見なされ、深刻な事態に発展するリスクを常に認識する必要があります。
担当者個人の資質に依存するのではなく、組織として投稿内容を精査する体制が求められます。
従業員のプライベートな投稿からの発展
従業員が個人で利用するSNSアカウントでの不適切な投稿が、企業の炎上につながるケースも頻繁に発生しています。
勤務先の情報や内部事情の漏洩、顧客や取引先への誹謗中傷、反社会的な内容の発信などが、第三者によって勤務先企業と結びつけられ、拡散されることで問題が大きくなります。
たとえ非公開アカウントであっても、スクリーンショットなどで情報が流出する可能性は否定できません。
従業員一人ひとりに対し、プライベートな発信であっても社会的な責任が伴うこと、そしてその言動が会社の評判に直結しうるという意識を持たせるためのリテラシー教育が不可欠です。
批判的な意見に対する不誠実な対応
自社の投稿や商品に対して寄せられた批判的な意見や指摘への対応を誤ると、炎上をさらに深刻化させることがあります。
批判コメントを無視したり、一方的に削除したり、あるいは感情的に反論したりする行為は、ユーザーから「不誠実」「隠蔽体質」と見なされ、さらなる非難を呼び起こします。
批判の中には、企業の成長につながる貴重な指摘が含まれていることも少なくありません。
たとえ耳の痛い意見であっても、まずは真摯に受け止め、冷静かつ丁寧に対応する姿勢が求められます。
企業としての対話の窓口を閉ざすような態度は、信頼を大きく損なう原因となります。
誤った情報の拡散やフェイクニュース
企業が公式アカウントとして発信する情報は、社会的に高い信頼性をもって受け止められます。
そのため、事実確認が不十分な情報や、誤った情報を発信してしまった場合、フェイクニュースの拡散に加担したとして厳しい批判を受け、炎上につながることがあります。
特に、災害時や社会的に注目度の高い出来事に関する情報を発信する際は、情報の正確性を期するために、公的機関などの一次情報を確認するプロセスが不可欠です。
善意からの情報提供であっても、結果として社会に混乱を招いた責任は免れず、一度失った信頼を取り戻すことは極めて困難です。
社会の価値観や倫理観とのズレ
過去には問題視されなかった表現や価値観が、時代の変化とともに許容されなくなり、炎上の原因となることがあります。
特に、ジェンダー平等、多様性の尊重、ルッキズム(外見至上主義)への批判、コンプライアンス意識の高まりなど、現代社会の倫理観と企業の発信するメッセージがズレている場合、強い反発を招きます。
企業活動での意思決定においては、常に社会の価値観がどのように変化しているかを敏感に察知し、自社の考え方をアップデートしていく姿勢が不可欠です。
古い価値観のままでは、意図せずして多くの人を傷つけ、企業の存続を危うくするリスクがあります。
SNS炎上が企業にもたらす深刻なリスク

SNS炎上は、単なるインターネット上の一時的な騒動ではありません。
炎上がもたらす影響はオンラインの世界にとどまらず、企業の事業活動全体に深刻なダメージを与える現実的なリスクです。
ブランドイメージの低下による顧客離れから、売上減少や株価下落といった直接的な金銭的損失、さらには従業員の離職といった組織内部の問題にまで発展する可能性があります。
ここでは、炎上が企業にもたらす具体的なリスクについて解説します。
企業ブランドイメージの著しい低下
SNS炎上がもたらす最も深刻なリスクの一つが、企業が長年にわたって築き上げてきたブランドイメージや信頼の著しい低下です。
一度、「顧客を軽視する企業」「差別的な企業」「不誠実な企業」といったネガティブなレッテルが貼られてしまうと、そのイメージを払拭することは極めて困難になります。
特に感情的な反発を招きやすい問題は、瞬く間に情報が拡散されやすく、消費者や取引先の信頼を根底から揺るがします。
失われた信頼を回復するためには、多大な時間と費用、そして地道な努力が必要不可欠です。
商品・サービスの売上減少
企業イメージの悪化は、消費者の購買行動に直接的な影響を及ぼし、商品やサービスの不買運動へと発展することがあります。
その結果、売上が大幅に減少し、企業の収益に深刻な打撃を与えます。
消費者は、問題を起こした企業の製品やサービスを積極的に避ける傾向が強く、代替品があればためらうことなく乗り換えるでしょう。
炎上が鎮火した後も、ネガティブなイメージは残り続け、一度離れてしまった顧客の心を再び取り戻すのは容易ではありません。
特に一般消費者を対象とするBtoCビジネスでは、このリスクは極めて大きくなります。
株価の下落や取引先からの信用失墜
上場企業におけるSNS炎上は、企業の将来性に対する投資家の不安を煽り、株価の急落を引き起こす直接的な要因となります。
特に炎上の原因が、法令違反やコーポレートガバナンスの欠如といった根深い問題に起因する場合、その影響は甚大です。
また、炎上は株主だけでなく、取引先からの信用失墜にもつながります。
コンプライアンスを重視する企業は、問題を起こした企業との取引を敬遠するようになり、契約の見直しや打ち切りに至るケースも考えられます。
社会的な信用の失墜は、企業の資金調達や事業継続そのものを脅かす重大なリスクです。
対応に追われる従業員の疲弊
SNS炎上の影響は、社外だけでなく社内にも及びます。
炎上が発生すると、顧客相談窓口や広報部門には、電話やメールによるクレーム、問い合わせが殺到します。
担当する従業員は、昼夜を問わずその対応に追われ、心身ともに極度のストレスに晒されることになります。
このような状況は、従業員のモチベーションを著しく低下させ、社内の雰囲気を悪化させます。
長期化すれば、優秀な人材の離職につながる可能性も否定できません。
組織全体の生産性が低下し、本来注力すべき業務が停滞するなど、企業活動の根幹を揺るがす内部リスクとなります。
SNSで炎上が発生した際の正しい対処フロー
どれだけ注意を払っていても、SNS炎上のリスクを完全にゼロにすることは困難です。
そのため、万が一炎上が発生してしまった場合に、いかに被害を最小限に抑えるかという観点から、正しい対処法を知っておくことが重要です。
初期対応のスピードと的確さが、その後の事態の収束を大きく左右します。
ここでは、炎上発生時に冷静かつ迅速に行動するための具体的な解決策と注意点を、ステップごとのフローで解説します。
ステップ1:事実関係を迅速に調査・確認する
炎上の兆候を察知したら、まず最初に行うべきは、何が起きているのかを正確に把握するための事実関係の調査です。憶測や不確かな情報に基づいて行動することは、事態をさらに悪化させる危険があります。
炎上の原因となっている投稿内容、拡散の範囲や速度、ユーザーからどのような批判が寄せられているのかといった情報を、SNS上ですぐに収集・確認します。並行して、投稿担当者や関連部署へのヒアリングを行い、客観的な事実を迅速に固めることが、その後の的確な判断の基礎となります。
ステップ2:社内の関係部署と情報を共有し方針を決定する
事実関係が把握できたら、次にSNS運用担当者だけでなく、広報、法務、顧客対応、関連事業部など、社内の関係部署間で速やかに情報を共有します。
必要に応じて、役員を含む対策本部を立ち上げ、組織として対応にあたる体制を整えます。
収集した情報をもとに、炎上の深刻度や影響範囲を冷静に分析し、会社としての方針を決定します。
謝罪の要否、謝罪文の内容、発表のタイミングや方法、原因となった投稿の削除の是非など、一貫性のある対応プランをここで具体的に策定します。
ステップ3:謝罪文の発表など誠意ある姿勢を示す
対応方針が固まったら、企業の公式サイトやSNSの公式アカウントを通じて、速やかにユーザーへの説明や謝罪を行います。
この際、言い訳がましく聞こえたり、責任の所在を曖昧にしたりする表現は、さらなる批判を招くため絶対に避けるべきです。
何が問題であり、誰を傷つけたのかを明確にし、真摯に反省の意を表明することが、事態の沈静化に向けた第一歩となります。
二次炎上を防ぐためにも、誠意が伝わる言葉を選び、企業の責任ある姿勢を明確に示すことが重要です。
ステップ4:再発防止策を策定し公表する
謝罪と当面の対応だけで終わらせず、なぜ今回の炎上が起きてしまったのかという根本的な原因を究明し、具体的な再発防止策を策定することが不可欠です。
例えば、SNS運用ガイドラインの見直し、投稿前のチェック体制の強化、従業員研修の実施などが挙げられます。
そして、策定した再発防止策は、社内での徹底はもちろんのこと、対外的にも公表することが望ましいです。
これにより、企業が問題に真摯に向き合い、本気で改善に取り組む姿勢を示すことができ、失われた信頼の回復に向けた重要な一歩となります。
炎上を未然に防ぐために企業がすべき事前対策
SNS炎上は、一度発生するとその対応に多大な労力とコストを要し、企業に深刻なダメージを与えます。
したがって、事後対応もさることながら、炎上そのものを起こさせないための予防策を平時から講じておくことが極めて重要です。
ルール作り、従業員教育、業務フローの整備といった多角的なアプローチによって、炎上のリスクは大幅に低減させることが可能です。
ここでは、企業が取り組むべき具体的な事前対策について解説します。
SNS運用に関するガイドラインを明確に定める
炎上を未然に防ぐための最も基本的な対策は、SNS運用に関する明確なガイドラインを策定し、全従業員に周知徹底することです。
このマニュアルには、投稿内容の基本方針、ブランドイメージを損なわないための言葉遣い、差別や人権侵害につながる表現の禁止、著作権や肖像権といった法令遵守事項、そして緊急時の連絡・報告体制などを具体的に明記します。
担当者の個人的な感覚や判断に依存する運用は非常に危険です。
組織としての統一された基準を設けることで、担当者が交代しても一貫した質の高い運用を維持し、不用意なミスによるリスクを最小限に抑えます。
従業員向けにSNSリスク研修を定期的に実施する
ガイドラインは作成するだけでなく、その内容が全従業員に正しく理解され、日々の行動に反映されなければ意味がありません。
そのため、SNSの利用に関するリスク研修を定期的に実施することが重要です。
この研修では、過去に他社で起きた炎上の具体的な事例を取り上げ、どのような投稿がなぜ問題になったのかを学ぶことで、従業員一人ひとりのリスク感度を高めます。
研修の対象は、公式アカウントの運用担当者だけでなく、全従業員とすることが理想です。
プライベートでのSNS利用が、結果として会社に重大な損害を与える可能性があることを理解させ、組織全体のITリテラシーを向上させます。
投稿前の複数人によるチェック体制を構築する
人間の注意力には限界があり、どれだけ気をつけていてもミスや見落としは起こり得ます。
担当者一人の判断で投稿を行う運用は、炎上リスクを高める非常に危険な行為です。
これを防ぐために、投稿を公開する前には必ず複数の目を通すチェック体制を構築することが不可欠です。
上長や同僚など、投稿者とは異なる視点を持つ人物が内容を確認することで、担当者自身では気づきにくい問題点(誤字脱字、不適切な表現、誤解を招く可能性など)を事前に発見できます。
特に重要な告知やキャンペーンに関する投稿は、法務部や広報部などの専門部署も交えた多重チェックが望ましいです。
炎上リスクを監視するツールを導入する
自社や自社製品に関するネガティブな言及や炎上の兆候を、人の目だけで24時間365日監視し続けるのは現実的ではありません。
そこで有効となるのが、SNS上の投稿を自動で収集・分析するソーシャルリスニングツールや炎上監視ツールの導入です。
これらのツールを活用することで、膨大な量の口コミの中から、批判的な投稿や急激に拡散されている投稿を早期に検知し、炎上が本格化する前に迅速な初期対応をとることが可能になります。
また、専門のコンサルティング会社と契約し、リスク分析や監視体制の構築について専門的な支援を受けることも有効な選択肢の一つです。
緊急時の対応マニュアルを準備しておく
どれだけ万全な予防策を講じても、炎上のリスクを完全にゼロにすることはできません。
そのため、万が一の事態が発生した際に、組織として迅速かつ的確に対応できるよう、緊急時の対応マニュアルをあらかじめ準備しておくことが極めて重要です。
このマニュアルには、炎上を発見した際の報告ルート、責任者や対策本部の設置手順、各部署の役割分担、社外への公式発表の手順、弁護士などの専門家への相談窓口などを具体的に定めておきます。
事前に詳細な行動計画を文書化しておくことで、有事の際にもパニックに陥ることなく、冷静沈着な対応が可能となります。
まとめ
本記事のまとめとして、SNS炎上は現代の企業活動において避けて通れない経営リスクであることが挙げられます。
その原因は、担当者の認識不足から従業員のプライベートな投稿、さらには社会の価値観とのズレまで多岐にわたります。
炎上はブランドイメージの低下や売上減少といった深刻な事態を招きますが、適切な対策を講じることでリスクを管理することは可能です。
平時からSNS運用ガイドラインを整備し、従業員への研修を徹底すること、投稿前のチェック体制や緊急時の対応マニュアルを準備しておくといった事前対策が、企業の信頼と未来を守る上で不可欠です。
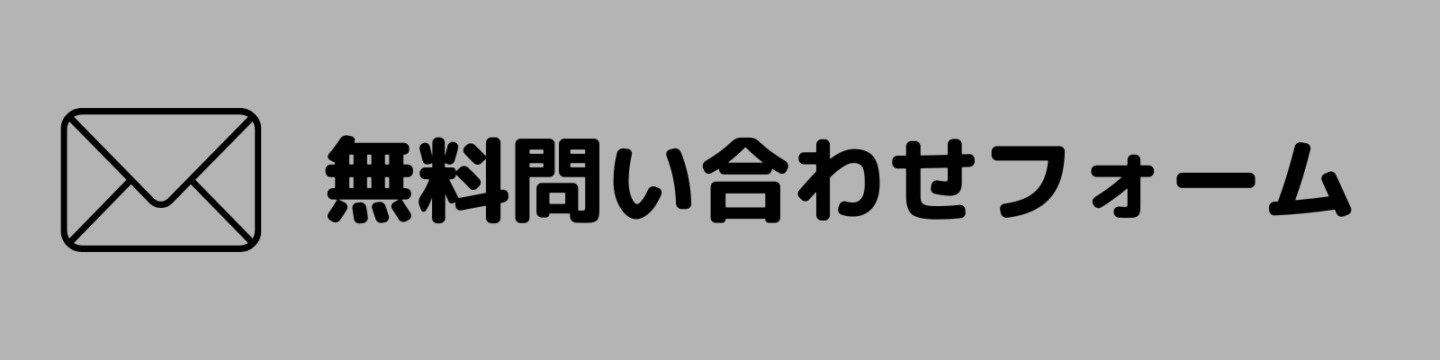
UCWORLDが選ばれる理由
SNS炎上への対策を万全にしても、 企業が見落としがちな重要な問題があります。
それが「炎上後の検索結果」です。
炎上は鎮火しても、検索サジェストは残り続ける
SNS炎上が落ち着き、 謝罪も済ませ、再発防止策も実施した。
しかし、Google検索で企業名を入力すると、 「企業名+炎上」「企業名+不買」といったサジェストが、 いつまでも表示され続けています。
これが、多くの企業が直面する現実です。
総務省の「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する調査研究」でも指摘されているように、 オンライン上の風評は長期的な影響を与えます。
炎上対策と検索結果管理は別物
多くの企業は、SNS炎上への対応として、 以下のような施策に注力します:
- SNS運用ガイドラインの策定
- 従業員研修の実施
- 投稿前チェック体制の構築
- 炎上監視ツールの導入
これらはもちろん重要です。
しかし、炎上が起きてしまった「後」の、 検索結果での評判管理まで手が回っている企業は、 ほとんどありません。
結果として、炎上から1年、2年が経過しても、 検索サジェストにはネガティブなキーワードが残り続け、 新規顧客の獲得や採用活動に悪影響を及ぼし続けます。
炎上後の検索結果が与える3つのダメージ

ダメージ1:新規顧客の獲得機会の喪失
商品やサービスに興味を持った見込み客が、 企業名で検索した際、 「炎上」「不買」というサジェストを見て、 購入をためらってしまう。
ダメージ2:採用活動への深刻な悪影響
就職・転職を検討している求職者が、 企業研究のために検索すると、 過去の炎上に関するサジェストが表示され、 応募を見送ってしまう。
ダメージ3:取引先や投資家からの信用低下
新規の取引先候補や投資家が、 デューデリジェンスの一環で企業を検索すると、 ネガティブなサジェストが表示され、 取引や投資を見送る判断材料になる。
UCWORLDの包括的なアプローチ

炎上への対応と並行して、 検索結果での評判管理も行う。
これが、現代企業に求められる包括的なリスク管理です。
UCWORLDは、企業の風評被害・ネガティブキーワード対策を、 技術的・戦略的にサポートします。
1. 検索サジェストの最適化
炎上後も残り続けるネガティブなサジェストを抑制し、 ポジティブなキーワードへと転換します。サジェスト対策サービスでは、 1キーワード3万円からという明確な料金体系で、 炎上後の評判回復を支援します。
2. ネガティブ情報の露出抑制
炎上時の記事や投稿が検索結果の上位に残り続けている場合、 その露出を抑制し、 企業の改善努力や現在の姿を伝える情報が、 上位表示されるよう設計します。
ネガティブワードの抑制だけでなく、 良質な関連語・指名語が自然に出る設計までセットで進めることで、 検索体験そのものをプラスに転換します。
(※良質な関連語・指名語の表示設計提案は別料金となります)
3. 約1週間での効果実感を目指すスピード対応
炎上後の評判回復には時間がかかると思われがちですが、 UCWORLDのサジェスト対策は、 適切な施策により約1週間程度で効果を実感いただけるケースもあります。
炎上のダメージを最小限に抑え、 一刻も早く通常のビジネスに戻るために、 迅速な対応が可能です。
炎上は「終わり」ではなく「始まり」
SNSでの炎上が鎮火したとき、 多くの企業は「やっと終わった」と安堵します。
しかし、それは本当の意味での「終わり」ではありません。
検索結果に残り続けるネガティブな情報が、 企業の評判を蝕み続ける。
これが、炎上後に待ち受ける「本当の戦い」です。
SNS炎上への予防策と対応策を整えることは重要です。
しかし、それと同じくらい重要なのが、 炎上後の検索結果での評判管理です。
まずは無料で現状診断を
過去に炎上を経験した企業、 あるいは現在炎上対応中の企業の担当者様。
自社の企業名で検索したとき、 どんなサジェストが表示されているか確認しましたか?
UCWORLDでは、無料でのご相談を承っています。
検索結果とサジェストの状況を分析し、 必要な対策と費用を明確にご提案いたします。
秘密厳守、相談のみでも大歓迎です。 まずはお気軽にお問い合わせください。
炎上対策とは、SNSでの火消しだけではありません。 検索結果での評判管理まで含めた、包括的な取り組みが必要です。

 お問い合わせ
お問い合わせ 資料請求
資料請求