- メディア
- 2025.10.22
BtoB企業がサービス名認知を獲得するための実践的戦略ガイド

BtoB企業にとって、サービス名の認知度向上は売上に直結する重要な課題です。しかし、BtoC企業のように大規模な広告予算を投じることは難しく、ターゲットも限定的なため、効率的な認知戦略が求められます。
本記事では、限られた予算でもサービス名の認知を効果的に高めるための実践的な戦略について、具体的な手法とともに解説します。

BtoB企業が直面するサービス名認知の課題
多くのBtoB企業は、優れたサービスを提供しているにもかかわらず、認知度の低さから商談機会を逃しています。
なぜBtoBでは認知獲得が難しいのか
BtoB市場特有の構造が、認知獲得を困難にしています。
まず、ターゲットが限定的であるため、マス広告の効果が薄いという問題があります。テレビCMや新聞広告に多額の予算を投じても、実際にサービスを必要としている企業の担当者に届く確率は極めて低くなります。
また、BtoB商材は購買プロセスが長く、複数の意思決定者が関与するため、単純な認知だけでは購買につながりません。サービス名を知っているだけでなく、どのような課題を解決できるのか、競合との違いは何かまで理解してもらう必要があります。
さらに、検索エンジンで自社サービス名を検索する人は、すでに何らかの接点を持った見込み客である可能性が高いものの、そもそもサービス名を知らない潜在顧客にはリーチできないというジレンマがあります。
従来の認知施策が機能しない理由
多くのBtoB企業が実施してきた従来型の認知施策は、費用対効果の面で課題を抱えています。
SEO対策は効果的な手法ですが、検索上位を獲得するまでに半年から1年以上かかることも珍しくありません。競合が多いキーワードでは、さらに時間がかかります。
リスティング広告は即効性がありますが、BtoB商材の場合、クリック単価が高騰しやすく、月額数十万円の予算を継続的に投下する必要があります。中小企業にとっては大きな負担です。
コンテンツマーケティングは有効な手法ですが、継続的に質の高いコンテンツを制作するには、専門人材の確保や外部パートナーへの委託費用が必要になります。
展示会への出展は直接的な接点を作れますが、1回の出展で数百万円の費用がかかり、獲得できるリード数も限定的です。
サジェスト対策がBtoB認知戦略の突破口になる理由
こうした課題を解決する新しいアプローチとして注目されているのが、サジェスト対策です。
検索行動の「入り口」で認知を獲得する仕組み
サジェスト対策の最大の特徴は、検索結果が表示される前の段階でサービス名を露出できることです。
潜在顧客が業界キーワードや課題を表すキーワードを検索窓に入力した瞬間、サジェストに自社サービス名が表示されます。これにより、まだ自社を知らない見込み客に対して、自然な形で認知を獲得できます。
例えば、「営業支援」と入力したユーザーに対して「営業支援 ○○(自社サービス名)」とサジェスト表示されれば、ユーザーは「このサービスは多くの人が検索しているのだろう」と認識し、信頼感
サジェストは広告表示ではないため、ネットリテラシーの高いBtoB担当者にも自然に受け入れられやすいという特性があります。
BtoB企業に最適な3つの理由
サジェスト対策がBtoB企業に適している理由は明確です。
第一に、月額3万円から始められる手頃な価格設定です。大規模な広告予算を確保できない中小企業でも継続的に実施できます。
第二に、効果が表れるまでのスピードが速いことです。早ければ1週間程度でサジェストに表示され始めるため、SEO対策のように長期間待つ必要がありません。
第三に、クリック課金ではなく表示課金であるため、予算管理がしやすく、想定外のコスト増加が発生しにくいという安心感があります。
業界キーワードとサービス名を紐付ける戦略設計
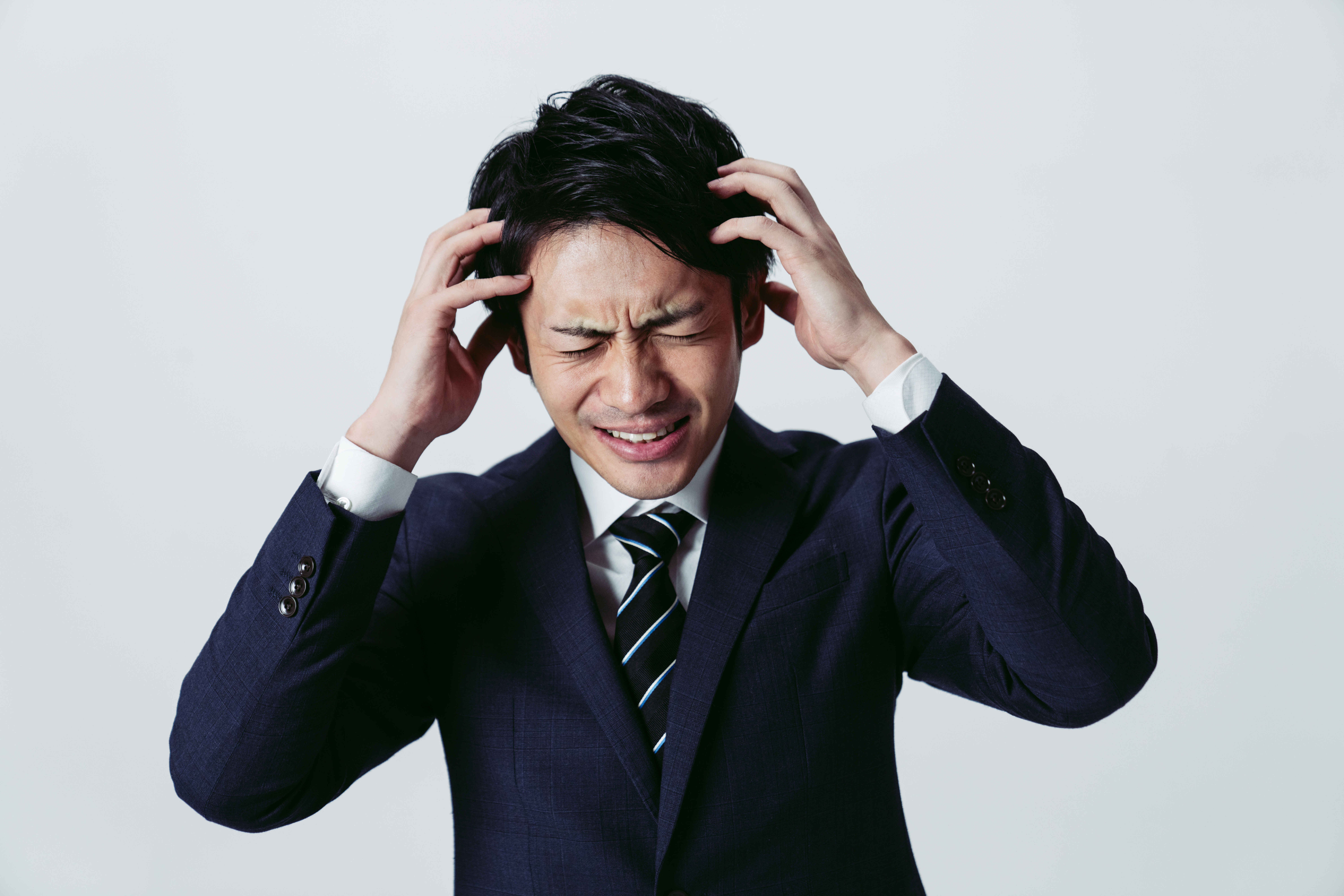
効果的な認知戦略を実現するには、適切なキーワード設計が不可欠です。
ターゲットの検索行動を徹底分析する
サジェスト対策で成果を出すには、ターゲットがどのようなキーワードで検索しているかを正確に把握する必要があります。
まず、自社サービスが解決する課題を言語化します。「営業効率が悪い」「人事評価が属人的」「在庫管理が煩雑」など、顧客が抱えている具体的な悩みをリストアップします。
次に、それらの課題を検索する際に使われるキーワードを洗い出します。Googleキーワードプランナーやラッコキーワードなどのツールを活用し、検索ボリュームを確認します。
重要なのは、検索ボリュームが多すぎても少なすぎても効果が薄いということです。月間検索数が1,000〜10,000回程度のキーワードが、BtoB企業には適していることが多いです。
3階層のキーワード戦略を構築する
サービス名認知を段階的に高めるために、3つの階層でキーワードを設計します。
第1階層:業界・課題キーワード
「クラウド会計」「人材育成」「物流管理」など、業界や課題を表す広範なキーワードです。検索ボリュームは大きいものの、競合も多いため、まずは認知のベースを作る目的で活用します。
これらのキーワードで「業界キーワード + 自社サービス名」というサジェストを表示させることで、潜在顧客層への露出を増やします。
第2階層:ソリューション・機能キーワード
「営業自動化ツール」「クラウド勤怠管理」「AIチャットボット」など、具体的なソリューションや機能を表すキーワードです。
このレベルのキーワードで検索するユーザーは、すでに何らかの解決策を探している段階にあります。サジェストで自社サービス名を表示させることで、比較検討の候補に入ることができます。
第3階層:競合・比較キーワード
「競合A 代替」「サービスB 比較」「○○ツール おすすめ」など、比較検討段階のキーワードです。
このレベルまで来ると、ユーザーの購買意欲は非常に高くなっています。競合名と組み合わせて自社サービス名をサジェスト表示させることで、比較検討の土俵に上がることができます。
認知から検討、そして商談へつなぐ導線設計
サジェストで認知を獲得しても、その後の導線がなければ商談につながりません。
サジェストからの流入を最大化するランディングページ
サジェスト経由で自社サービス名を検索したユーザーは、高い関心を持っています。このユーザーを確実に次のステップへ導くには、最適化されたランディングページが必要です。
まず、ファーストビューで「誰のどんな課題を解決するサービスなのか」を明確に伝えます。BtoB担当者は時間がないため、3秒以内に判断できる情報設計が重要です。
次に、具体的な導入効果を数値で示します。「作業時間50%削減」「コスト30%削減」「売上20%向上」など、定量的な成果を提示することで、説得力が増します。
導入事例や顧客の声を掲載し、社会的証明を示すことも効果的です。特に同業他社や有名企業の導入実績があれば、信頼性が大きく高まります。
段階的なコンバージョンポイントを設置する
BtoB商材は高額かつ導入の意思決定に時間がかかるため、いきなり「お問い合わせ」を求めても成果は出にくいです。
段階的なコンバージョンポイントを設置することで、さまざまな温度感のユーザーを取り込めます。
軽いコンバージョン:資料ダウンロード
サービス概要をまとめた資料や、導入事例集、業界レポートなど、有益な情報を提供することで、まだ検討初期段階のユーザーの情報を獲得できます。
中間コンバージョン:ウェビナー参加
サービスの活用方法や業界トレンドをテーマにしたウェビナーを開催し、参加者を募ります。ウェビナーは双方向のコミュニケーションが取れるため、関係構築に有効です。
重いコンバージョン:無料トライアル・デモ申込
実際にサービスを体験してもらうことで、導入後のイメージを具体化できます。このレベルまで来たユーザーは、かなり温度感が高いと判断できます。
最終コンバージョン:お問い合わせ・商談申込
具体的な導入を検討しているユーザー向けに、個別相談や見積もり依頼の窓口を用意します。
他施策と組み合わせた統合的認知戦略
サジェスト対策を単独で実施するのではなく、他の施策と組み合わせることで、相乗効果が生まれます。
コンテンツマーケティングとの連携
自社メディアやブログで業界の課題解決に関する有益なコンテンツを発信し、SEO経由での流入を増やします。同時に、サジェストで自社サービス名の露出を高めることで、コンテンツを読んだユーザーが「このサービスを詳しく知りたい」と思ったときに、すぐに検索して見つけられるようになります。
コンテンツ内で自社サービス名を自然に言及することで、サジェストのアルゴリズムにもプラスに働く可能性があります。
SNS戦略との相互補完
LinkedInやTwitter(X)などのSNSで業界の専門家としてのポジションを確立し、フォロワーを増やします。SNSで認知したユーザーが詳しく知りたいと思ったときに、検索窓でサービス名がサジェストされれば、スムーズに公式サイトへ誘導できます。
SNSでの発信内容とサジェストで表示させるキーワードを連動させることで、ブランドメッセージの一貫性を保てます。
ウェビナー・セミナーとの組み合わせ
オンラインやオフラインでウェビナーやセミナーを開催し、直接的な接点を作ります。参加者は高い関心を持っているため、イベント後にサービス名で検索する可能性が高くなります。
このタイミングでサジェストに自社サービス名が表示されれば、「やはり注目されているサービスなのだ」という印象を強化できます。
リスティング広告との効率的連携
サジェスト対策で認知度が高まると、自社サービス名での指名検索が増加します。この指名検索に対してリスティング広告を配信することで、高いコンバージョン率を実現できます。
指名検索のクリック単価は一般キーワードよりも低いため、費用対効果が高くなります。詳しくはリスティング×サジェスト連携術の記事もご参照ください。
業種別のサービス名認知戦略事例
業種によって最適なアプローチは異なります。
SaaS・クラウドサービス企業
SaaS企業では、機能や用途を表すキーワードでサジェスト対策を実施します。
例えば、「プロジェクト管理ツール」「タスク管理アプリ」「工数管理システム」などのキーワードで、自社サービス名をサジェスト表示させます。
無料トライアルへの導線を強化し、実際にサービスを体験してもらうことで、認知から導入までのプロセスを短縮できます。
コンサルティング・専門サービス
コンサルティング会社では、課題や悩みを表すキーワードが効果的です。
「DX推進 支援」「業務効率化 コンサル」「組織改革 アドバイザー」などのキーワードで、自社のサービスブランド名やプログラム名をサジェスト表示させます。
事例やホワイトペーパーのダウンロードから始め、段階的に関係性を深めていくアプローチが適しています。
製造業・BtoB卸売
製造業やBtoB卸売では、製品カテゴリーや用途でのサジェスト対策が有効です。
「産業用ロボット メーカー」「精密部品 サプライヤー」「業務用厨房機器 卸」などのキーワードで、自社ブランド名を表示させます。
カタログダウンロードや製品紹介動画の視聴を入り口として、営業担当者へのつなぎを行います。
人材・教育サービス
人材紹介や教育研修サービスでは、採用や育成に関するキーワードが重要です。
「エンジニア採用 支援」「管理職研修 プログラム」「新卒育成 カリキュラム」などで自社サービス名をサジェスト表示させます。
セミナーやウェビナーへの参加を促し、対面での関係構築につなげる戦略が効果的です。
効果測定と継続的な改善サイクル
認知戦略は一度実施して終わりではなく、継続的な改善が必要です。
測定すべき5つの指標
サジェスト対策の効果を正確に把握するには、複数の指標を追跡します。
まず、Google Search Consoleで自社サービス名での検索数の推移を確認します。サジェスト対策開始前と比較して、どの程度増加しているかを測定します。
次に、Googleアナリティクスで自然検索からの流入数とコンバージョン数を追跡します。特に、サービス名での検索経由のコンバージョン率は重要な指標です。
サジェストの表示状況も定期的にチェックします。ターゲットとしているキーワードで、実際にサジェストに自社サービス名が表示されているかを確認します。
ランディングページの直帰率や滞在時間も重要です。サジェスト経由の流入がページから離脱せず、次のアクションに進んでいるかを見ます。
最終的には、商談数や受注数への影響を測定します。認知獲得からどれくらいの期間で商談化しているかを追跡することで、ROIを算出できます。
3ヶ月ごとの見直しサイクル
BtoB商材は検討期間が長いため、少なくとも3ヶ月単位で効果を評価します。
最初の3ヶ月は、サジェスト表示の安定化と指名検索数の増加に注力します。この段階では、まだ商談数への直接的な影響は見えにくいかもしれません。
4〜6ヶ月目は、流入したユーザーのコンバージョン率改善に取り組みます。ランディングページの最適化や、コンバージョンポイントの調整を行います。
7ヶ月目以降は、獲得したリードの育成と商談化に焦点を当てます。マーケティングオートメーションツールを活用し、適切なタイミングで適切な情報を提供します。
限られた予算で最大の認知を獲得するために
BtoB企業にとって、サービス名の認知度向上は避けて通れない課題です。しかし、大規模な広告予算がなくても、戦略的なアプローチによって効果的に認知を獲得できます。
サジェスト対策を中心に据え、他の施策と組み合わせることで、認知から商談までの一貫した導線を構築できます。
重要なのは、短期的な成果を求めすぎず、中長期的な視点で継続的に取り組むことです。3ヶ月、6ヶ月、1年というスパンで効果を評価し、改善を重ねていくことが成功への道筋となります。
専門家と共に最適な認知戦略を構築する
サービス名認知戦略を自社だけで設計し実行するのは、専門知識と経験が必要です。特に、サジェスト対策は検索エンジンのアルゴリズムを理解した上で、適切なキーワード選定と施策実行が求められます。
UCWORLDでは、BtoB企業のサービス名認知戦略について、サジェスト対策を軸とした統合的な支援を提供しています。貴社の業界特性やターゲット顧客の行動パターンを分析し、最適な認知戦略を設計いたします。
月額3万円からという手頃な価格で始められるため、まずは小さくテストし、効果を確認しながら拡大していくことが可能です。
サービス名の認知度を高め、商談機会を増やしたいとお考えの企業様は、ぜひお問い合わせください。現状の課題をヒアリングさせていただき、具体的な施策プランをご提案いたします。

 お問い合わせ
お問い合わせ 資料請求
資料請求